| ★32 |
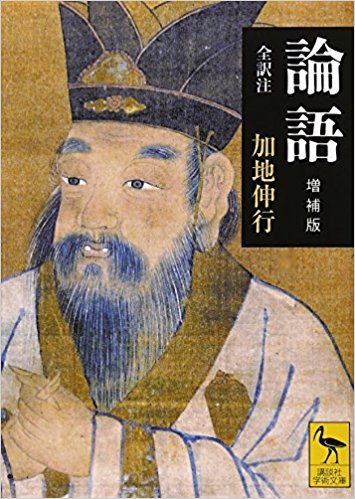 | 論語 |
Content
内容紹介
人間とは何か。溟濛の時代にあって、人はいかに生くべきか。現代と交響する至高の古典に、われわれは親しみ、学んできた。だが、さらに多くの宝石のよ...▽
名言抜粋
(他人に対して人当たりよく)こ...
夫婦はたがいに相手の良いところ...
その人物の日常生活の現在をしっ...
古人の書物に習熟して、そこから...
知識や情報を(たくさん)得ても...
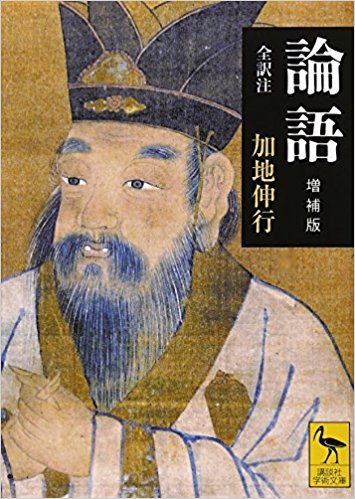 | 論語 孔子 amazon で見る |
一緒に閲覧されている本
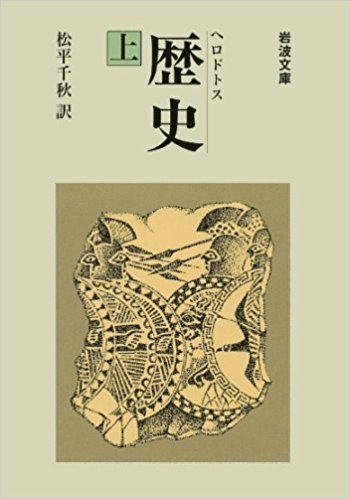 | 歴史 上 ヘロドトス |
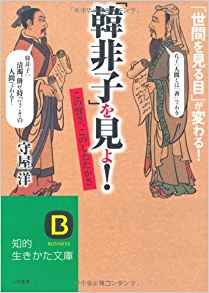 | 「韓非子」を見よ 韓非 |
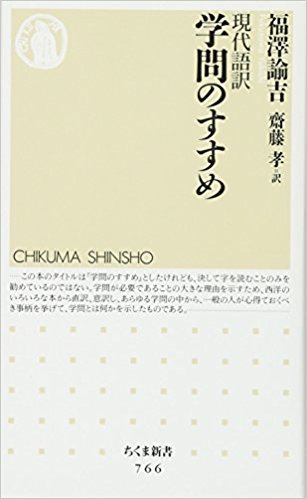 | 学問のすすめ 福澤諭吉 |
 | エセー 1 モンテーニュ |
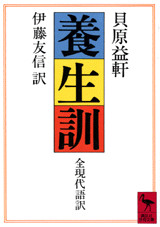 | 養生訓 貝原益軒 |
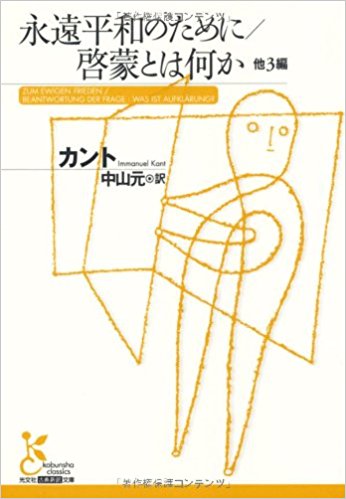 | 永遠平和のために カント |
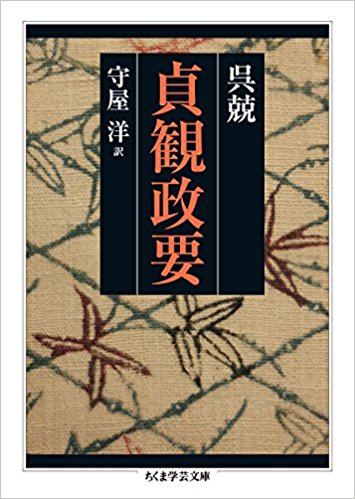 | 貞観政要 呉兢 |
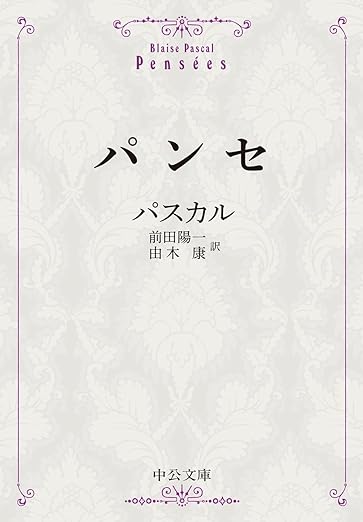 | パンセ パスカル |
 | 老年について キケロ |
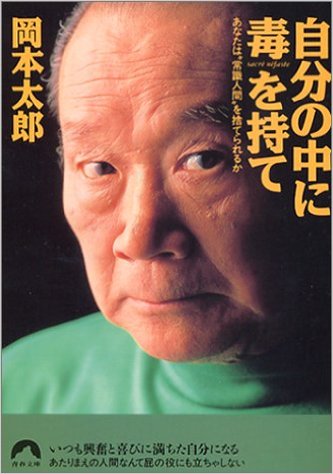 | 自分の中に毒を持て 岡本太郎 |
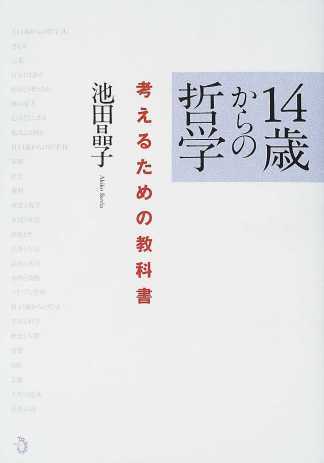 | 14歳からの哲学 池田晶子 |
 | ゴルギアス プラトン |


