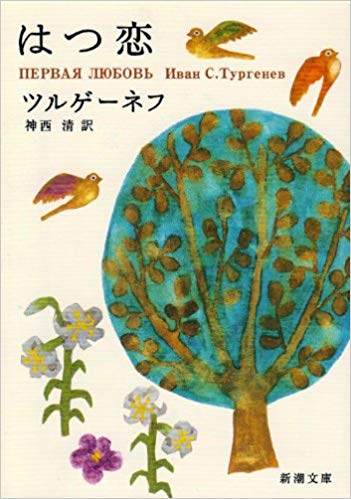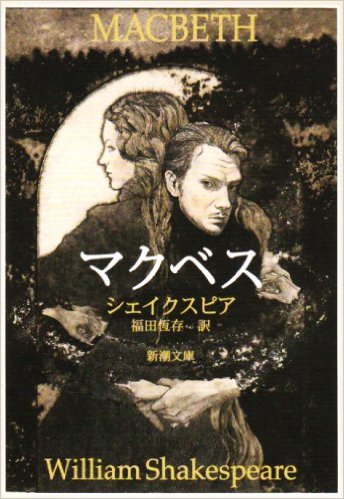名著ランキング
61
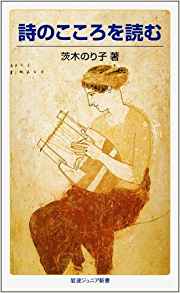 | 茨木のり子 |
いい詩には、人の心を解き放ってくれる力があります。また、生きとし生けるものへのいとおしみの感情をやさしく誘いだしてもくれます。この本では、長いあいだ詩を書き、多くの詩を読んできた著者が、心を豊かにしつ... | |
62
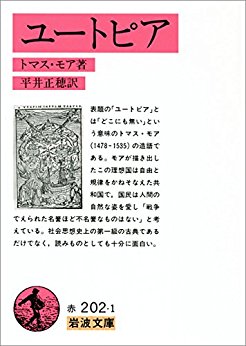 | トマス・モア |
表題の「ユートピア」とは「どこにも無い」という意味のトマス・モア(1478‐1535)の造語である。モアが描き出したこの理想国は自由と規律をかねそなえた共和国で、国民は人間の自然な姿を愛し「戦争でえら... | |
63
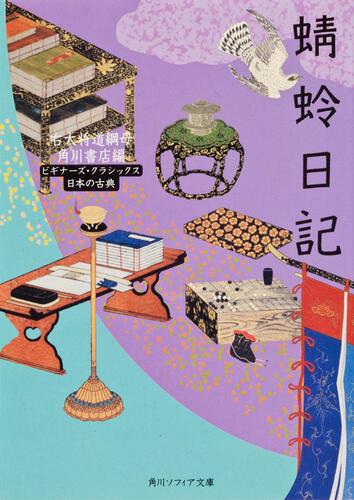 | 藤原道綱母 |
美貌と歌才に恵まれ権門の夫をもちながら、蜻蛉のようにはかない身の上を嘆く藤原道綱母の21年間の日記。鋭く人生を見つめ、夫の愛情に絶望していく心理を繊細に描く。現代語訳を前面に出し、難解な日記をしっかり... | |
64
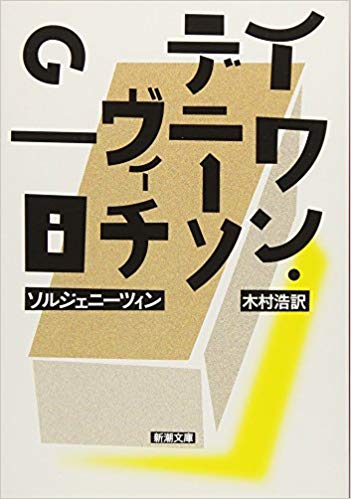 | ソルジェニーツィン |
1962年の暮、全世界は驚きと感動で、この小説に目をみはった。当時作者は中学校の田舎教師であったが、その文学的完成度はもちろん、ソ連社会の現実をも深く認識させるものであったからである。スターリン暗黒時... | |
65
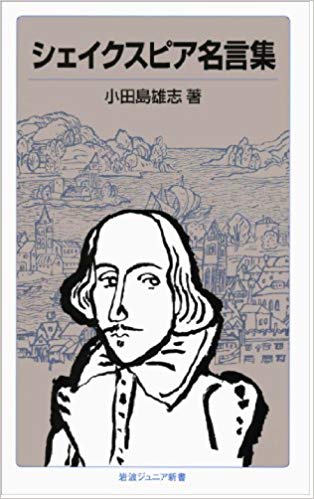 | シェイクスピア |
「このままでいいのか、いけないのか、それが問題だ」(ハムレット)、「人生は歩きまわる影法師、あわれな役者だ」(マクベス)など、シェイクスピアの言葉は、世界中の人びとに愛誦されています。これらの名言を豊... | |
66
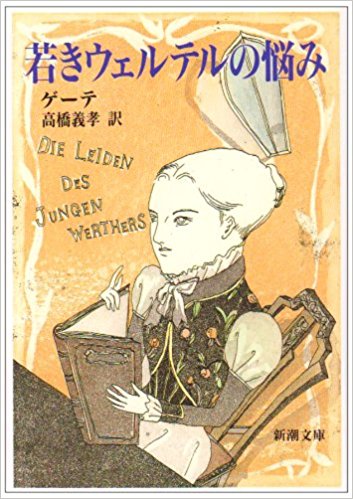 | ゲーテ |
ゲーテ自身の絶望的な恋の体験を作品化した書簡体小説で、ウェルテルの名が、恋する純情多感な青年の代名詞となっている古典的名作である。許婚者のいる美貌の女性ロッテを恋したウェルテルは、遂げられぬ恋であるこ... | |
67
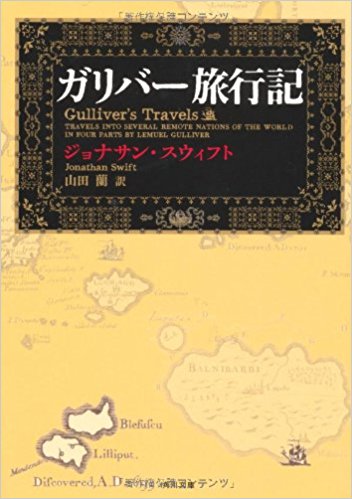 | ジョナサン・スウィフト |
小人たちの国、巨人たちの国、空飛ぶ島の国、馬たちの国…イギリスに妻子を残し、懲りずに旅を続けたガリバー。彼が出会ったおとぎの国々を、誰もが一度は夢見たことがあるだろう。子供の心と想像力で、スウィフトが... | |
69
 | コクトー |
14歳のポールは、憧れの生徒ダルジュロスの投げた雪玉で負傷し、友人のジェラールに部屋まで送られる。そこはポールと姉エリザベートの「ふたりだけの部屋」だった。そしてダルジュロスにそっくりの少女、アガート... | |