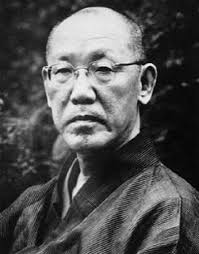
大きな会社に入ると、人は堕落する傾向があ...
 |  | ≒ |  | #勉学 |
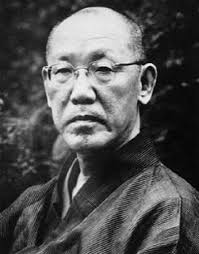 | ||||||
大きな会社に入ると、人は堕落する傾向があ... | ||||||
| ||||||
 | ||||||
孤独というのはいいものだ。友情もいいけど... | ||||||
| ||||||
 | ||||||
友人にその欠点を教えるのは、友情のもっと... | ||||||
| ||||||
 | ||||||
遠方に離れている友人が1年も2年も音信不... | ||||||
| ||||||
 | ||||||
お金は社会の力をあらわすための大切な道具... | ||||||
| ||||||
 | ||||||
日本がめざすべきは、経済大国でも軍事大国... | ||||||
| ||||||
 | ||||||
この仕事は、自分にとって意味があるだろう... | ||||||
| ||||||
 | ||||||
気持ちがゆったりとして豊かな人は、春の風... | ||||||
| ||||||
 | ||||||
企業の実態がマーケットや株価に反映される... | ||||||
| ||||||
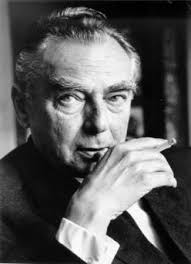 | ||||||
教師たるものはな、つねに成長、変化する能... | ||||||
| ||||||