Answer
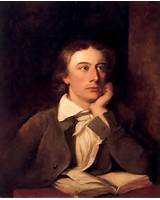 | ジョン・キーツ 詩人 | |||||
美しいものは永遠なる喜びである。 | ||||||
| ||||||
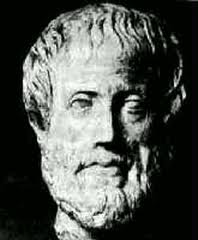 | ||||||
「美しいこと」や「正しいこと」には多くの... | ||||||
| ||||||
 | ||||||
青春は美しいというのは、そこを通りすぎて... | ||||||
| ||||||
 | ||||||
今まで出会った中で最も美しいと感じたのは... | ||||||
| ||||||
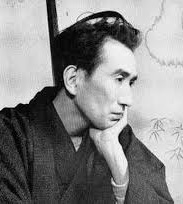 | ||||||
孤島の波打際(なみうちぎわ)に、美しい人... | ||||||
| ||||||
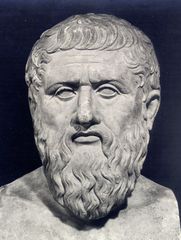 | ||||||
(民主主義は)様々の国制のなかでも、いち... | ||||||
| ||||||
 | ||||||
私は愛情のすべてを注ぎ、できる限りの世話... | ||||||
| ||||||
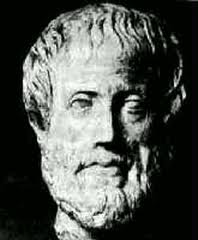 | ||||||
「頭のよさ」と呼ばれる能力がある。これは... | ||||||
| ||||||
 | ||||||
もしも人間が憎悪がもとでやっているすべて... | ||||||
| ||||||
 | ||||||
憎しみは、ほかのどんなものよりもエネルギ... | ||||||
| ||||||
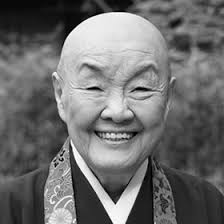 | ||||||
お釈迦様は「この世は苦だ」とおっしゃいま... | ||||||
| ||||||