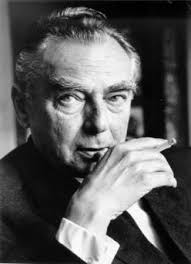
教師たるものはな、つねに成長、変化する能...
 |  | ≒ |  | #勉学 |
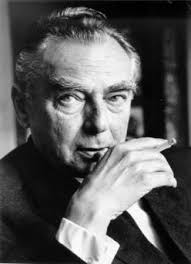 | ||||||
教師たるものはな、つねに成長、変化する能... | ||||||
| ||||||
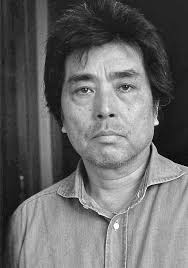 | ||||||
いい大学に行って、いい会社や官庁に入れば... | ||||||
| ||||||
 | ||||||
みずからを高めるのは有益です。また、自分... | ||||||
| ||||||
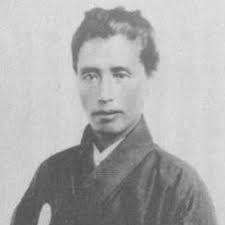 | ||||||
教師の名前はカッテンデーケ(ヴィレム・カ... | ||||||
| ||||||
 | ||||||
果たして、浅慮、無責任、我無者らの職業軍... | ||||||
| ||||||
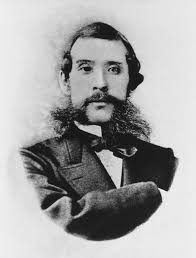 | ||||||
そもそも国家人民のためにその責任ある者は... | ||||||
| ||||||
 | ||||||
組織の機能の向上を求めるならば、 責任の... | ||||||
| ||||||
 | ||||||
人間であるということは、とりもなおさず責... | ||||||
| ||||||
 | ||||||
ディオクレティアヌスは、 専従にすること... | ||||||
| ||||||
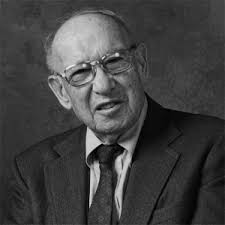 | ||||||
真のリーダーは、他の誰でもなく、自らが最... | ||||||
| ||||||