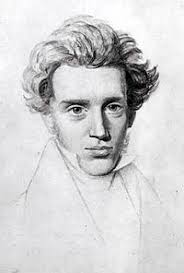
青年が人生並に自己自身について並外れた希...
 |  | ≒ |  | #年齢 |
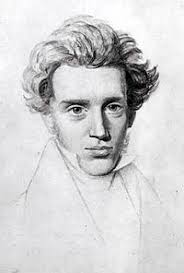 | ||||||
青年が人生並に自己自身について並外れた希... | ||||||
| ||||||
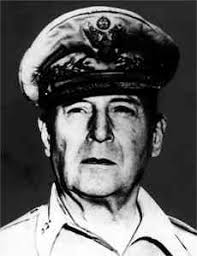 | ||||||
科学、美術、宗教、文化などの発展の上から... | ||||||
| ||||||
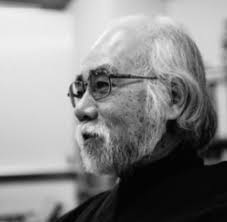 | ||||||
美人が老醜を恐れるように、輝かしい青年時... | ||||||
| ||||||
 | ||||||
誰かがいとも高いところから四方を見わたす... | ||||||
| ||||||
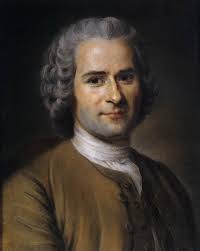 | ||||||
青年時代は知恵を磨く時であり、老年はそれ... | ||||||
| ||||||
 | ||||||
さて、人格を磨くための方法や工夫は色々と... | ||||||
| ||||||
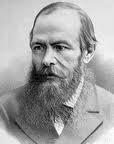 | ||||||
幼年時代の思い出から得た神聖な貴重なもの... | ||||||
| ||||||
 | ||||||
老いてからの欠乏を補うのに十分なものを青... | ||||||
| ||||||
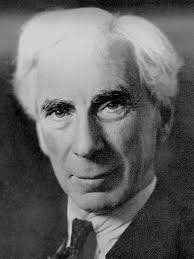 | ||||||
多少とも単調な生活に耐えうるという能力こ... | ||||||
| ||||||
 | ||||||
青年時代には不満はあっても 悲観してはな... | ||||||
| ||||||