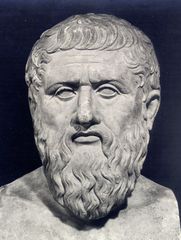
(民主主義は)様々の国制のなかでも、いち...
 |  | ≒ |  | #政治 |
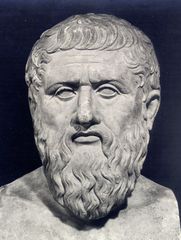 | ||||||
(民主主義は)様々の国制のなかでも、いち... | ||||||
| ||||||
 | ||||||
「もっとも、知事は結局空騒ぎだと確信して... | ||||||
| ||||||
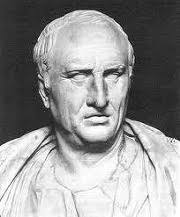 | ||||||
無知の無経験な者が治療薬のかわりに人を殺... | ||||||
| ||||||
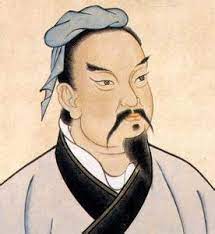 | ||||||
戦争前に「五事七計」を検討すれば、勝敗は... | ||||||
| ||||||
 | ||||||
共和国または王国の安寧秩序は、その生命の... | ||||||
| ||||||
 | ||||||
人間は富と権力に対する欲に憑りつかれてい... | ||||||
| ||||||
 | ||||||
しかし、国民の先頭に立つべき洋学者が、や... | ||||||
| ||||||
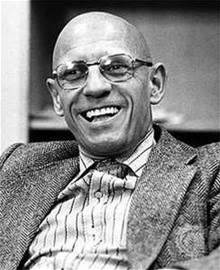 | ||||||
重要なのは、処罰技術が身体刑の祭式で身体... | ||||||
| ||||||
 | ||||||
王国であれ、また共和国であれ、一つの共同... | ||||||
| ||||||
 | ||||||
保護と指図は表裏一体であるべきだ。国で例... | ||||||
| ||||||