
陸海軍の間では、「相互の中枢における長年...
 |  | ≒ |  | #組織 |
 | ||||||
陸海軍の間では、「相互の中枢における長年... | ||||||
| ||||||
 | ||||||
社会はわれわれの必要から生じ、政府はわれ... | ||||||
| ||||||
 | ||||||
一言で言えば、退屈の反対は快楽ではなく、... | ||||||
| ||||||
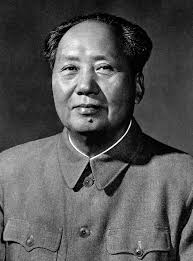 | ||||||
政治とは、流血を伴わぬ戦争である。一方、... | ||||||
| ||||||
 | ||||||
神経症的な愛を生む基本的条件は、「恋人た... | ||||||
| ||||||
 | ||||||
猫は、貴族のようなもので、(何もせずとも... | ||||||
| ||||||
 | ||||||
平衡感覚とは、 互いに矛盾する両極にある... | ||||||
| ||||||
 | ||||||
他者に害を与えたら責任を問われる。これは... | ||||||
| ||||||
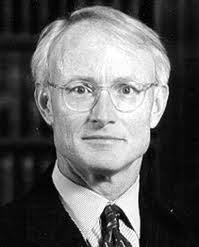 | ||||||
日本企業の歴史的な強みと個性は、組織の全... | ||||||
| ||||||
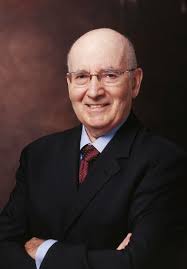 | ||||||
いままでは顧客の調査を重ねれば、「顧客の... | ||||||
| ||||||