
最後に、日本には独立した学問がない。学問...
 |  | ≒ |  | #勉学 |
 | ||||||
最後に、日本には独立した学問がない。学問... | ||||||
| ||||||
 | ||||||
オリガルキーにおける君主の専制は、民衆の... | ||||||
| ||||||
 | ||||||
政治と軍事の関係適正化には、閣議に軍の最... | ||||||
| ||||||
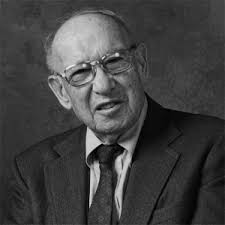 | ||||||
取締役会の衰退はあらゆる国で見られる。理... | ||||||
| ||||||
 | ||||||
立法府と行政府が同一の人物または機関で結... | ||||||
| ||||||
 | ||||||
立法府と行政府が同一の人物または機関で結... | ||||||
| ||||||
 | ||||||
日本では古来、政府と人民は敵対関係と言っ... | ||||||
| ||||||
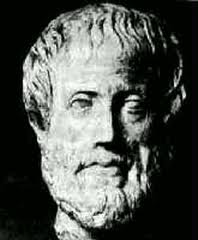 | ||||||
国家体制には、支配者人数と善政か悪政かで... | ||||||
| ||||||
 | ||||||
自由と秩序の両立は、人類に与えられた永遠... | ||||||
| ||||||
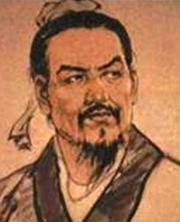 | ||||||
国が安泰であるか危険であるかは「是非」、... | ||||||
| ||||||