
教育家の配慮がどんなに行き届いても、生ま...
 |  | ≒ |  | #勉学 |
 | ||||||
教育家の配慮がどんなに行き届いても、生ま... | ||||||
| ||||||
 | ||||||
机に座って読書するだけを学問だと思うのは... | ||||||
| ||||||
 | ||||||
これほど、自分の想像を裏切った相手を知ら... | ||||||
| ||||||
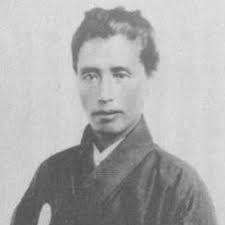 | ||||||
時勢は、人を造るものだ。今日いろいろの学... | ||||||
| ||||||
 | ||||||
教育者が注意すべきは、活ける社会に立ち万... | ||||||
| ||||||
 | ||||||
賢者と接したら良い部分を吸収し、父母のも... | ||||||
| ||||||
 | ||||||
生まれが同時代、仕事が同業、といった身近... | ||||||
| ||||||
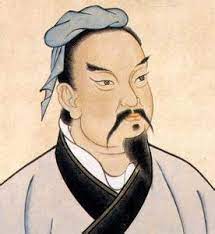 | ||||||
出来るのに出来ないふりをする。用いている... | ||||||
| ||||||
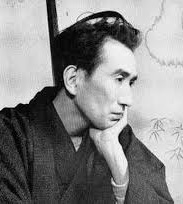 | ||||||
小さい時にどんな教育を受けたかという事で... | ||||||
| ||||||
 | ||||||
君子たる者、落ち着きがなければ威厳が感じ... | ||||||
| ||||||