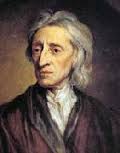
社会にとって必要不可欠なもの、すなわち、...
 |  | ≒ |  | #社会 |
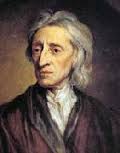 | ||||||
社会にとって必要不可欠なもの、すなわち、... | ||||||
| ||||||
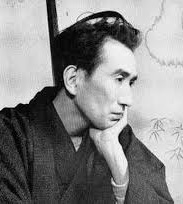 | ||||||
一人の外国文学者が、私の「父」という短篇... | ||||||
| ||||||
 | ||||||
世界の人民は礼を空気として、徳の海に浴し... | ||||||
| ||||||
 | ||||||
現代という時代は、人類史上かつてないほど... | ||||||
| ||||||
 | ||||||
愛の対象にせよ、物質にせよ、地位や名誉に... | ||||||
| ||||||
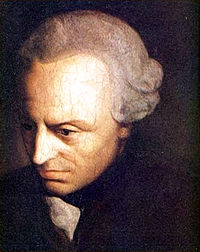 | ||||||
民族は自然状態においては、すなわち外的な... | ||||||
| ||||||
 | ||||||
いちばん先に正しいことを行なうがよい。正... | ||||||
| ||||||
 | ||||||
われわれの状態は、あまりにも人工的で複雑... | ||||||
| ||||||
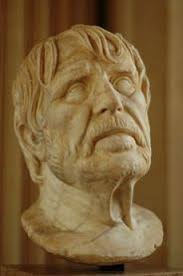 | ||||||
あんまりきちんとしすぎていて、定期的に特... | ||||||
| ||||||
 | ||||||
贅沢とは浪費することであり、浪費するとは... | ||||||
| ||||||