
テレビが普及していったときに、ジャーナリ...
 |  | ≒ |  | #仕事 |
 | ||||||
テレビが普及していったときに、ジャーナリ... | ||||||
| ||||||
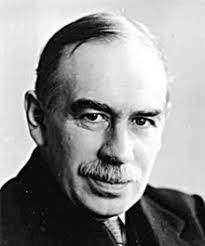 | ||||||
今日我々になしうることのすべては、我々の... | ||||||
| ||||||
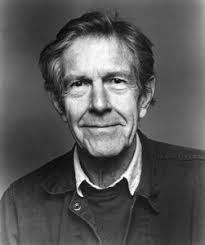 | ||||||
欧州では、人々が絶えず自分の傘を開こうと... | ||||||
| ||||||
 | ||||||
この、なんか、人がボロボロ崩れていくよう... | ||||||
| ||||||
 | ||||||
国際社会には現状維持的傾向があり、バラン... | ||||||
| ||||||
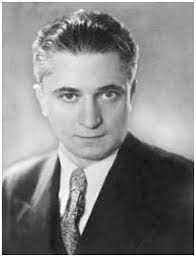 | ||||||
しかし、この傾向が見られるのはヨーロッパ... | ||||||
| ||||||
 | ||||||
私の本来の傾向は、すべてを思想に転換する... | ||||||
| ||||||
 | ||||||
全然傾向が違いますけれども、堀越二郎と本... | ||||||
| ||||||
 | ||||||
人類は農業革命によって、手に入る食糧の総... | ||||||
| ||||||
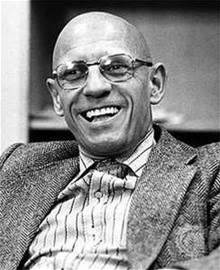 | ||||||
重商主義時代の大々的な人口増加論から、目... | ||||||
| ||||||