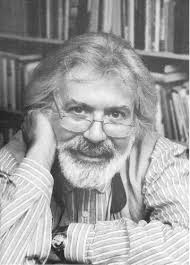
『はてしない物語』で展開されたのは、もは...
 |  | ≒ |  | #政治 |
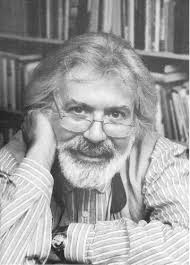 | ||||||
『はてしない物語』で展開されたのは、もは... | ||||||
| ||||||
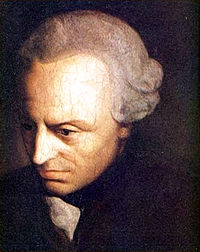 | ||||||
モラルある政治家は、国にとってなにが最善... | ||||||
| ||||||
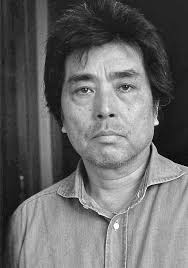 | ||||||
過去の政治形態は歴史です、歴史にモラルは... | ||||||
| ||||||
 | ||||||
共同体といっても、家庭や学校といった狭い... | ||||||
| ||||||
 | ||||||
偏狂とは、行いが一方に片寄って、常識から... | ||||||
| ||||||
 | ||||||
世界の人民は礼を空気として、徳の海に浴し... | ||||||
| ||||||
 | ||||||
まず、日本には独立した市民がいない。日本... | ||||||
| ||||||
 | ||||||
日本でも中国でも西洋でも、慈悲深い君主が... | ||||||
| ||||||
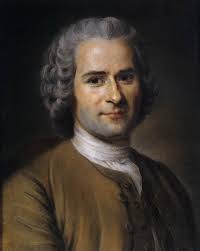 | ||||||
そのためには、市民は自分たちが持つ財産や... | ||||||
| ||||||
 | ||||||
(君主は)愛されるよりも恐れられる方がは... | ||||||
| ||||||